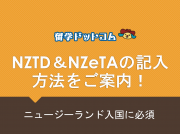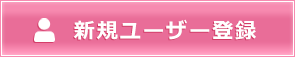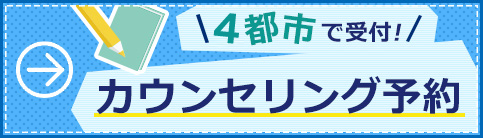人を動かすカリスマ性、動かされる人々がいる、そんな「キング」の話 (1)

「キング」ってなんだろう、と時々思う。
辞書によると、「国や特定の領土、部族などの長たる者。またある特定の分野の頂点に立つもの。」とある。頂点って一人じゃない?「点」だから。「線」じゃないしね。
その割には、キングって言葉よく聞くなと思う。キングカズ、キングオブコメディ、ドンキーング、スティーブンキング、めちゃくちゃいる。それに音楽やダンス、エンターテインメント界全体で言っても、かなりキングがいるような気がする。
エルヴィスプレスリーもキングの名称で親しまれているけど、実際本当のキングが誰なのか。人によってかなり意見が違うと思う。だけど自分がアメリカに来て、キングという称号を良く聞く人がいる。
マイケルジャクソンだ。これは自分がファンだからではなく、実際に本当によく聞くのだ。今まで日本にいた時から、本当に大好きだったマイケルだけど、アメリカで見たり聞いたりする彼の姿は日本のそれとは大分違う。そこはやっぱり彼の母国であるから、良くも悪くも印象は強い。
初めてアメリカに来た16歳の時、語学学校の寮まで送ってくれていたドライバーの人が、なんでアメリカに来たのか聞いてきた。だから、マイケルジャクソンが好きで来たというと、黒人の40代くらいの彼は笑いながら、「この土地で彼のことを好きな人はそれ程いないよ。」と言ったことは今でも忘れない。
いや、たった30分前に初めてアメリカに来た16歳の男の子に、そんなこと言うかね?と思ったのもあったし、「いや、そんなはずはない。マイケルは凄いんだ。」こいつは一体何を言っているんだ、と思ったことも忘れない。
それから高校生活をアメリカで過ごしていくにつれて、何度マイケルに助けられてきたか分からない。マイケルのダンスをしたら必ずウケた。マイケルのおかげでかなり印象が残って、そこから仲良くなった人も山ほどいる。
あれだけひとつの動きで誰もが分かって、盛り上がるのはマイケルがそれだけアイコニックだったからで、その事実はゴシップがどうあろうとも変わらなかった。
彼が亡くなって、そして自分が彼に恋をしてから10年。10年前初めてキャプテンEO(マイケルジャクソン主演の世界各国のディズニーランドで上映されたアトラクション)を観て衝撃を受けた時、まさかその10年後にアメリカにいて、マイケルと踊った人達と会って、一緒に踊っている姿なんて全く想像できていなかった。
あの時の十数分が、本当に人生を変えた。初めてマイケルの踊っている姿を見てから、本当に狂ったようにマイケルだけを見続けた。そんな時間を過ごしたから、今ロサンゼルスで生活していてもマイケルを至るところに感じる。これはもしかしたら自分だけの視点かもしれないと気づいたので、ここでその視点をシェアできたらと思う。
これは想像以上に大きな記事になってしまったので、二週に分けてお届けしたいと思う。マイケルファンの皆さん、どういたしまして。(笑)そうでない皆さん、ごめんなさい、お付き合いください…。
人を動かすということ
マイケルジャクソンと聞いた時、まず思い付くことは何だろう?白く光る手袋?ムーンウォーク?スリラー?それとも数多くのゴシップ?たくさんのイメージが良くも悪くも付きまとい、それはこれから先も拭われることはないだろう。
実際、今でもアメリカのラジオで、”Beat It”, “The Way You Make Me Feel”など彼の曲がよくかかっているし、彼の写真がハリウッドのセブンイレブンにマリリンモンローと一緒に飾られているのを見ると、アメリカの一部であるように感じている。
死してなお、なぜそこまで人を惹きつけるのか。人によってこれも意見は分かれると思うけど、自分の体験を含めた視点で書いていきたいと思う。
・ダンス
これはほぼ全ての人が同意してくれると思う。だって彼のダンスは本当に凄いから。彼のダンスは、ジャンルでいうとジャズダンスがルーツの振り付けで始まり、彼自身もフレッドアステア等のスター達にインスパイアされた振り付けや、体のラインを綺麗に見せるような動きを、放課後に幼い時から兄弟達とベルトを片手に持った父の指導の下練習していたのは有名な話。
いわゆる「白人らしい」綺麗な動きから、ジェームスブラウンのような「熱」で魅せる動きも幼い頃位から見てきたマイケル。そのバランス感覚はそのままに、タップダンスやロボットダンスを習得していた10代。ここまで見ても、彼はたくさんのジャンルからインスパイアされていたのがわかる。
そこからは皆さんご存知”Thriller”、”Beat It”といったシンガーがダンサーを率いて踊るというミュージックビデオのスタイルを初めて確率したのだ。ミュージカル「映画」のクオリティを、いわゆるミュージックビデオに持ってきたのは彼が初めてだった。わざわざこだわって「ショートフィルム」と呼んだのも彼だ。
もし彼がそこまでしていなかったら、今のダンサーというポジションは職業にすらなっていなかったかもしれない。今沢山の人がダンススタジオに通い、ポップアーティストと踊るのを夢みているけど、マイケルがいなかったらそんな当たり前すらなかったかもしれない。
ダンススタジオが一回のレッスンで15ドルを取って、それでビジネスとして回っていくという当たり前を作った人の一人はマイケルであると思う。
というのも、”Smooth Criminal”や”Will You Be There”といった有名な曲を振り付けたダンサーVincent Patersonが言っていたのが、「マイケルがビートイットで沢山の男のダンサーを引き連れて踊るまで、男のジャズダンサーは本当に少なかったんだ。でも彼は、『マイケルと踊る』という大きな目標を示してくれた。それからダンス学校の男の志願者は一気に増えたんだ。」とのこと。
その時代をリアルタイムで生きて、活躍してきた人が証言しているということは、本当に大きな変化を生んだのだろう。そんな背景があるから、アメリカのダンス文化とマイケルジャクソンというのは切っても切れない関係なのだ。
個人的に、マイケルが好きな人は踊りを見ればすぐにわかる。マイケルの動きをしていなくても、どこかにマイケルのエッセンスが感じられるのだ。
それは恐らく他の人達から見てもそうで、自分も踊ると、「マイケル好きでしょ?」と声を掛けられるのはしょっちゅうだ。沢山のジャンルを消化し、昇華させたマイケルのスタイルは本当に唯一無二だと感じさせられる。
・楽曲
マイケルの代表曲はあまりに沢山ある。この間ノースハリウッドの駅前を歩いていたら、アイスクリーム屋さんから”Remember The Time”が流れてきたり、毎年ハロウィーンの季節になると30年以上前の曲”Thriller”がビルボードの週刊チャートにランクインしてきたりと、マイケルの曲はそこら中に溢れていて、未だに愛されている。
何故それほどまでに聞かれているのか。それはまず、メロディーのキャッチーさがあると思う。彼はいつも、メロディーを大切にしていた。例え英語が分からない人や子供が聞いても、口ずさめるものを目指していたそう。非現実的なまでに世界中に向けて曲を作っていた。
それを歌う人によってはスケールが大きすぎて少し可笑しく感じてしまいそうなところを、自然に聞かせてしまう。それは彼があまりに現実離れした存在というのもあるかもしれないけど、やっぱり彼が本気で信じていたから出来たことだと思う。
人は不思議なもので、何を馬鹿なことをいっているんだと思うことでも、本気で話しているのがわかると、「もしかしたら事実かも…。」と思うものである。彼の「本気」が、未だにアメリカでは生きているから、あらゆるところで彼の音楽を耳にするのだろう。
じゃあ、ひたすらメルヘンで夢のようなことを歌い続けていたかというと、それは違う。人種差別について、彼の感じていた孤独について、壊されていく環境について、そして彼を苦しめ続けたメディアについてなど、しっかりと「リアル」も描いていたのだ。
それは彼だけの体験したリアルではなく、誰もが違ったレベルで共感できる、日常に溢れたリアルだった。アフリカの飢餓の時、21世紀に差し掛かろうとしていた時、あるいは9.11の直後も、彼はどんな状況でも世界のリアルを音楽を通して映してきた。
時代は違えども、そのメッセージはどれも普遍的で、今聴いても当てはまる問題が提起されている。それは簡単なようで難しいことじゃないか。40年近くソロで活躍したマイケルだから、やっぱり音も時代によってかなり違う。
そこはやっぱりアメリカ、音楽のメジャージャンルやスタイルはめまぐるしく変化している。今ではポップミュージックと言われるジャンルでさえ、EDM寄りの音になった10年後にはアトランタやマイアミから生まれたトラップを筆頭とするヒップホップのサウンドにかなり近づいている。
そんな流れの早い音楽業界の最先端、なんなら少し先を行く音作りもマイケルの音楽が長く親しまれている理由ではないだろうか。
あらゆる人種と文化が交わる国ということは、ロック、R&B、カントリー、ヒップホップといった多種多様なジャンルが聴かれる国ということでもある。だからこそ、ひとつのアルバムに沢山のジャンルが詰まった彼の作品が今でも親しまれているんじゃないかと思う。
例えば、彼のアルバム”Dangerous”を聴いてみて欲しい。アルバム序盤でラップを大々的にフィーチャーして、世の中の問題をあたかもストリートから提起したと思えば、アルバム後半では世界平和を子供達のコーラスと一緒に、そして一人の人間としての叫びをゴスペル隊を率いて歌うのである。
この振り幅にはカニエ・ウエストもびっくりではないだろうか。というかマイケルがこういった作品を創っていなければ、カニエやチャンス・ザ・ラッパーも後の革新的な作品を創ることはなかったかもしれない。この作品を80年代後半という、ラップやヒップホップがメジャーシーンに出てきてからまだ間もない頃に創ったマイケルは、文化の多様性というアメリカの特徴を無意識でも念頭に置いていたのだと思っている。
・ルックス
マイケルジャクソンという存在を語る上で、彼の見た目というのは必要不可欠な要素であると思う。短い黒のスラックスから見える白い靴下、右手の指先の白いテープ、光り輝くジャケットの数々、そしてどんな時でもずれることなく彼のシルエットを作り出していたフェードラハットなど、挙げていくと本当にキリがない。
「マイケルジャクソンらしい」というアイテムは無数にある。ただその下にあった彼の肌こそ、良くも悪くも彼のアイデンティティだったと思う。
彼は黒人として、インディアナ州のゲイリーという貧しい地域に生まれた。彼が兄弟達とジャクソン5としてデビューした頃は、黒人のチャイルドスターという存在は今よりも珍しく貴重な存在だった。
そんな姿は黒人のコミュニティに自信をくれたと語る人も多い。だから、「黒人のチャイルドスター」としての印象からスタートしたという背景がある。
それからティーン時代を経て、21歳になりソロアルバムをリリースした時、彼はまだ黒い肌と大きなアフロヘアを持っていた。
それから少しずつ彼の肌の色は明るくなっていき、29歳になってリリースしたアルバム、”BAD”ではほとんどアジアンのような肌の色と、流れるようなパーマがかかったロングヘアに変貌を遂げている。
この辺りから、今までマイケルを「黒人のチャイルドスター」の時代から知っている人々は困惑し始めた。彼の肌はどうなってしまったのか。変化していく音楽性と彼のルックスは、彼は白人になりたがっているなどという、あらぬ噂までもを生み出すこととなる。
白人と黒人という、色だけではない「違い」は、アメリカで生活していて凄く感じる。彼らは肌の色が違うだけで、同じだけ優しくて同じだけ素敵な存在なのは言うまでもないが、彼らのカルチャーは明らかに違う。
それは多文化な国であるから当たり前のこと。我々日本人が、幼い頃に三味線などの和の音を聞ける環境で育ったように、昔はより、白人はカントリーやロックが近くて、黒人はジャズやラップが近かった。話し方や感情表現の仕方など、細かいけど大きな違いは潜在的にも、少なからず今も残るカルチャーの違いだと思う。そこには差別なんてなくて、ただの違いである。
それは良いとか悪いとか、ジャッジされるものでもない。そんな「違い」を音楽的に自在に行き来するようになったマイケルが、今度は肌の色まで変わったとなると、人々が困惑するのも無理ないのかもしれない。そこにマイケルがどう思っているとか事実はどうなのかとか、そういったことは考慮されなかった。
事実は簡単なことで、彼は肌の色素が抜ける病気を患っていたという、ただそれだけのことだった。「尋常性白斑」という、肌の色がまだらになってしまう病気だったので、それをカバーするためにメイクしていた。だんだんと白い肌の面積が増えていったから、白いメイクでカバーせざるを得なくなった。ただそれだけなのだ。
マイケルは黒人という自分のルーツを、世界中の黒人の人と同じぐらい誇りに思っていた。だけど肌の色が変わったということだけで、昔ジャッジをされていた側の黒人からもジャッジされてしまった。悲しいけど、人は本当に見た目に左右されやすい生き物なのかもしれない。猫や犬は、互いの毛の色が違っても何も変わらない。目に見えないものに「目を向ける」ことの大切さが分かるのが、人の強さであり義務であると、このことを考える度に思う。
動かされた人達

マイケルに動かされて人生が変わった人は、あなたが思う以上にいる。きっと、いつもローファーに白い靴下を履いている同僚も実はマイケルファンかも知れない。
もしかしたら、あなた自身もマイケルから影響されているかもしれない。これから紹介する誰かが好きであれば、あなた間接的にもマイケルに影響されている。
大袈裟に言ってしまえば、マイケルなしには彼らはいない。ここで紹介するのは、沢山いる中のごく一部の、マイケルに動かされた有名な人達である。
クリスブラウン
今では不動のR&Bスターである彼も、もちろんマイケルのファンである。2006年にはMTVビデオミュージックアワードにて、マイケル本人から指名されてスリラーをカバー、パフォーマンスした。2014年リリースの楽曲”Fine China”は、ダンスパフォーマンスやストーリー仕立てのミュージックビデオ込みで、マイケルイズムを存分に感じる作品。
カニエ・ウエスト
先述の通り、彼もマイケルの大ファン。マイケル本人とマイケルの伝説的アルバム、スリラー25周年盤でコラボも果たしている。そしてほぼ毎アルバムに1曲はマイケルのことを扱う歌詞が出てくるカニエさん。
キャリア初期のインタビュー、そして最近のインタビューでも一貫して、「”She got a light-skinned friend look like Michael Jackson. Got a dark-skinned friend look like Michael Jackson(彼女はマイケルみたいな明るい色の肌をしていて、マイケルみたいな黒い肌の友達を持っている。)” という歌詞を書いた時、俺は絶対成功すると思ったよ。」というカニエ節を炸裂させている。
”All Of The Lights”という曲も、マイケルの死と彼自身に起こった出来事を引き合いに出し、混乱と不安を歌った名曲。この曲のミュージックビデオでもマイケル愛を感じることができる。
ビヨンセ
初めて行ったアーティストのライブがマイケルの初ソロツアー、BADツアーだったというビヨンセ。2000年代のアワードショーでもマイケルとステージ上で共演を果たしているし、2016年のスーパーボール(年に一度のフットボールの大きな試合)ハーフタイムショーではマイケルさながらの衣装で登場。
コーチェラ(アメリカで最も大きな野外音楽フェスの一つ)での伝説的なパフォーマンス(Netflixで観れるので気になる方はチェックしてみて!こちらでも黒人女性として生きる彼女の魂を観ることができます!)では、マイケルが兄弟達と歌った曲”Can You Feel It”を引用するなど、随所にマイケルへのトリビュートを捧げている。
マイケルが最後のライブを行うはずだった会場で、彼女が行ったライブのラスト、”Halo”のトリビュートパフォーマンスはいつ観ても涙が出る。
The 1975
イギリスはマンチェスター出身の4人組ロックバンド。最近は日本でもサマーソニックでの圧巻のパフォーマンスで認知度が上がってきている彼ら。ポップやロック、オルタナティブをも乗りこなす彼らの音楽にどこかマイケルらしさを感じるな、と思っていたらそれもそのはず。
ボーカルでフロントマンのマシューヒーリーはマイケルの大ファンで、「幼い頃はただただマイケルになりたかったんだ。」とインタビューで語っている。その影響からか幼い頃にはダンスも習っていたらしく、最近のミュージックビデオではマイケルさながらのダンスを披露している。
2016年リリースの曲、”This Must Be My Dream”は80年代のマイケルを彷彿とさせるスタジアムポップである。最新アルバムからの一曲、”Love It If We Made It”ではマイケルの名曲”The Way You Make Me Feel”へのダンスオマージュも捧げている。マイケル愛が彼らの作品の至るところに散りばめられている。
今週はここまで。
来週もマイケルだらけだけど、どれもカルチャーに密接に関わっているから、いつまでもマイケルは教えてくれるなぁと痛感させられています。