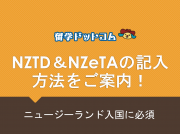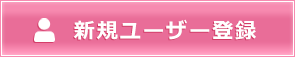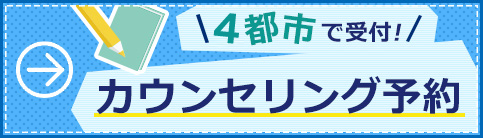フィクションだけどノンフィクション!?アメリカを感じられる映画を紹介 (後編)

習慣というかイメージというか、なぜか映画を観ていると無性にポップコーンが食べたくなる。そもそも映画館でポップコーンをあまり頼むタイプではないのに。そのくせ友達が食べているのはちゃっかり頂く。
そして、ポップコーンを食べていると、なぜか映画を観たくなる。いつもポップコーンを食べながら観ると、だいたいは序盤のあたりで完食してしまうか、集中し過ぎてポップコーンの存在を忘れてしまい、映画の終わりに残るのは胸の興奮と、手元のしなっとしたポップコーンだったりする。
そもそもなぜあんなサクサク音のする食べ物が映画館で売られているのか、少し不思議に思っていた。確かにポテトチップスと違い小さなカスは落ちないので、何かを観ながら食べるのには適しているのかも知れない。だけどあんなに音がするものじゃなくてもいい気がする。
映画館とポップコーンの馴れ初めを調べてみると、理由は意外なものだった。
それは昔に映画館で他のスナック等も販売していた時代があるらしく、その当時映画の内容が面白くないとブーイングと一緒にスクリーンにものが飛んできたらしい。
その当時の様々な映画館スナックの中には固いものもあり、スクリーンを傷つけてしまっていたらしい。そこで困った映画館側は、投げられてスクリーンに当たってもダメージが少ないポップコーンをメジャーにして販売し出したのが理由とのこと。
ブーイング対策として押し出されたポップコーン、歴史を知るとなかなか健気なものである。今では投げられる心配もないポップコーンだが、未だにポップコーンは映画とベストフレンドなのである。
日本の映画館でも、様々な味のポップコーンが売られている。そして、テーマパークさながらのバラエティに富んだポップコーンバケットも大きな特徴である。
味ももちろんなのだけれど、そういったスーベニア系のクオリティーが高いのが日本の特徴だろう。
では現在のアメリカのポップコーン事情はというと、フレーバーの種類などは割とオーソドックスである。キャラメル、バター、チーズとベースのフレーバーはこんなところ。
だが、ノースハリウッドの映画館のチーズは半端じゃなかった。
チェダー、アメリカンなどといった豊富な種類のチーズフレイバーの粉を、自分で好きなだけポップコーンにかけて味を付けるのである。
こうなってくると結構無法地帯で、なんでもありである。どれだけ味を濃くしようが、どれだけの種類をかけようがそれは完全にあなたの自由である。個人的にはチェダーチーズが美味しかったのを覚えている。
ちなみに今自分は猛烈に食べたい。それではポップコーンを用意して頂いて、おすすめの「アメリカを感じられる映画」をぜひチェックしてみて欲しい。
Begin Again (2013)
一見マイナスで、悪く見える出来事も長い目で見たらそれは結局自分や周りのプラスになっていたりしたことはないだろうか?きっとそのようにネガティブな出来事をポジティブに捉えることが出来た時に、本当の意味でそれを「乗り越えた」ということなのではないだろうか。
この映画は、タイトル通りそういった「再スタート」をテーマにしている映画である。監督・脚本に現代音楽映画のパイオニア的名作、「ONCE~ダブリンの街角で」を手がけたジョンカーニー。
主題歌/キャストに大人気ポップロックバンド、マルーン5のボーカルであるアダムレヴィーンや、今や司会や映画に引っ張りだこの「カープールカラオケ」でおなじみジェームズゴーデンを迎えるなど豪華な布陣で作られた今作。
アダム演じるデイブと、彼の恋人でシンガーソングライターのグレタは共にニューヨークにやってくるが、デイブの浮気を期にグレタはニューヨークを離れようと決意する。帰郷前夜に友達に促されて嫌々ながらもグレタが歌ったバーに、「元」敏腕音楽プロデューサーで今や妻や子供にも愛想を尽かされてしまった、ダンが居合わせる。そこから彼はグレタに、一緒にアルバムを作ろうと持ちかける…というのがあらすじ。
まず今作に出てくる音楽全てが、よくある映画のぬるっとしたポップ音楽ではなく、どれも超一流の上質な音楽であるということがこの映画の特徴。それもそのはず、あのアダムレヴィーンが携わっているのだ。たまにこの手の映画に出てくる音楽は、劇場でテンションが上がってサウンドトラックを買っても、次の日に改めて聴いてみると「あれ、劇中で聴いた時の方が良かったな。てかアレンジ違う?え、同じ?」みたいなことが起こったりする。
だけどこの映画の曲は、曲単体で聴いてもどれもが名作なのだ。そんな良質な音楽がストーリーと結びついた時、こちらの心に訴えかけない訳がない。そんな映画オリジナル曲以外にも、スティービーワンダーやフランクシナトラといった選曲センス抜群のクラシックな名曲も、適所で存分に使われている。
では、音楽ベースのプロモーションビデオみたいな作りになってしまっているのかというと、そういう訳でも全くない。しっかりとその曲が生まれるまでの感情の移り行きや、キャラクターそれぞれの背景がこれでもかとばかりに鮮明に表現されている。
今では歌手としてお馴染みの、若き日のヘイリースタインフェルドが演じるダンの娘、バイオレットの「父親不在」から来る父との距離感への悩み、学校の男の子との接し方やそもそも自分をどうやって見つければいいのか…そんな思春期の悩みなど、彼女ひとりだけとっても沢山のものを抱えて生きている。
浮気をしてしまったデイブ、ダンと別居中の妻ミリアム、グレタを支える友人スティーブ、みんなそれぞれが何かを抱えて生きている。その「何か」が曲と一緒に解放されて、シェアされていく。
それぞれがある意味で「自分をさらけ出す」プロセスを見ていると、現実世界と同じくこの映画には悪者はいないのだということに気づかされる。そういったある意味リアルな物語の紡ぎ方により、これはよくあるただただキャッチーな音楽映画とは一線を画している。
この映画のアメリカらしさは、ずばりそのニューヨークの街並みだろう。他のどのニューヨーク映画よりも、ベタ(=王道)なニューヨークの名所を惜しむことなく撮影地にしている。何よりその場所の特性を生かして曲をレコーディングしていく様を見ていると、そのアイディアに脱帽&感動。
音楽を通してそれぞれの過去を乗り越え、今を生きることでそれらをいい過去に変えようとする彼らが奏でる「はじまりのうた」は、あなたの心を揺さぶるに違いない。
(500)Days of Summer (2009)
前回のコラムで紹介した映画も含めると、音楽オタクの自分らしくどうしてもミュージカルや、音楽がストーリーの軸にある映画を選んでしまうようだ。確かに、どんな映画にも音楽というのは必要不可欠だし、大切な要素であることは間違いない。
では、逆の場合はどうだろう?音楽にも、ミュージックビデオという形態で映像はいつも不可欠だ。今作の監督、マークウェブはミュージックビデオの監督として、マイリーサイラスやマルーン5、ダニエルパウダーといったポップシンガー達をはじめ、グリーンデイやマイケミカルロマンスといったロックバンド達のミュージックビデオを数多く手がけてきた売れっ子。
そんな彼が長編映画初監督作品として発表したこの作品は、ゴールデングローブ賞を始めとする数多くの賞を受賞した、インディペンデント映画としては異例のヒット作。そんなマークが今までミュージックビデオで表現してきた、「日常生活に溢れている小さな大事件」をここでも見事に表現している。
グリーティングカード(お祝い事に送るメッセージ付きのカード)会社で働く主人公トムが、新しく入ってきた秘書のサマーに恋に落ちていく様子と、その失恋から立ち直っていくというラブコメディ。先述の通り、トムがサマーと出会って一目惚れしてからの生活は、「小さな大事件」で溢れていた。その誰もが恋に落ちた時に感じたことのある、そんな感覚を巧みに表現している。
彼女の小さなホクロまでも愛おしく思ってしまったり、彼女といい関係になった後の景色はミュージカル映画並みに底抜けに明るく見えたり。クスッとしてしまって、「バカだなぁ」と思ってしまうと同時に、トムへの共感とそんな二人を可愛く思ってしまう自分もいたりする。特にIKEAに二人で行くシーンは、見ているこちらが恥ずかしくなってしまうぐらいに可愛い。
きっとこれらの出来事は、周りの人からしたら本当に些細な出来事なのだろう。だけどこちらにとったら、彼女の手の動き一つでさえも一大事なのだ。逆に、サマーの心が自分から離れていってしまっていることを悟ったトムの心の中がくっきり分かる後半のシーンを見たら、きっといつかの自分たちの頭の中をスクリーンで観ているような感覚になるだろう。そういう「もう周りなんて見えないよ!」という自分たちの代弁者が、トムなのである。
キャスティングもこの映画が多くの人に楽しまれた原因の一つなのは間違いない。こういう「可憐」っていう言葉が似合う女の子を演じさせたら敵無しのズーイーデシャネルと、平凡だけど芯の強い、さえないけれど優しい男の子感がぴったりなジョセフゴードンという二人も役にハマっている。
そして、脇役にも名優揃いで、今ではすっかりハリウッド女優として「キック・アス」などのヒット作での活躍も印象的なクロエモレッツは、トムの大人びた妹役として辛辣かつ的確なコメントで作品にユーモアとスパイスを効かせている。
この映画にはロサンゼルスの街並みが多く見られ、二人がぐっと仲良くなるカラオケバーは、レッドウッド・バー&グリル(Redwood Bar & Grill)という実際にあるお店だし、トムが大事な時に訪れる映画館も実際にあるミリオンダラー・シアター(Million Dollar Theatre)という映画館である。この映画を観てから訪れるロサンゼルスは、普段より少しドラマチックかも知れない。