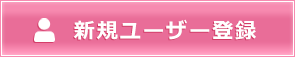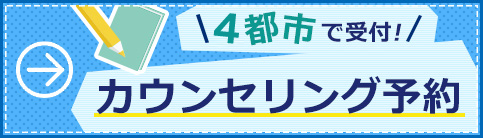アルバムというプラットフォーム ~アメリカから世界に!~

皆さんと同じく、ロサンゼルスにいる自分も「一人の時間」が激増している。このコロナでのロックダウンは、先日4月19日(日)までの予定だったのが、5月15日(金)まで延期になった。
そして、不要な外出には最悪で1,000ドル(日本円で10万円強)の罰金が課せられたり、マスク無しではスーパーマーケットにも入れてもらえなかったりなど、状況はまだ好転していないのが現状だ。
こうした中で、「いつもやろうと思っていたけど、急ぎではないこと。」をやり出したのは皆さんと同じな訳で…。
スティーブンコヴィー著の自己啓発本の金字塔、「7つの習慣」によると、こうした「重要度は高いが緊急性は低いもの」こそ自分を高めてくれることらしい。
確かに、オンラインの学校の課題だとか、このコラムを書くこととか、締め切りがあって大切なことはある。それらをやるのは当たり前だ。だけど、他のインスタグラムを眺めたり、買うものもないのにアーバンアウトフィッターズでほぼ毎日あるセールの項目を見ていたりする。
人間は、「緊急性も重要性も低いもの」に時間を割いていたりする。これは自分を高めることには直結しにくいだろう。こうしたことにも普段の生活ならあまり気にもしなかったことだろうが、今気付けたのはいつもより時間があるからである。
と言うことで、ようやく「緊急性は低いが重要性の高いもの」に手を付けられる時が自分の中で来たのだ。皆さんは、いったいどんなことを自分の中のリストに溜めていただろうか?
料理?筋トレ?英語学習?沢山のものがあるだろうが、自分はダントツ一番でやりたいことがあった。それはアルバム鑑賞だ。いつもツイッターやインスタグラム、街角でかかっていた曲をスキャンしまくったシャザームなどで知った、溜まりまくった聴きたい音楽達。
「いつかはしっかり聴き込むぞ!」と思いつつ、寝かせていたものは思っていた3倍の量があった。そもそも、アルバムというのは音楽を表現する上で必要不可欠なプラットフォームである。
プリンスが2015年のグラミー賞で、”Albums, remember those? Albums still matter. Like books and black lives, albums still matter(アルバムを覚えているかい?アルバムは今でも重要だよ。本や黒人の命と同じように、アルバムは今でも重要なんだ。)“と言っていたが、自分は100%同意だ。
今ではMigosとかDrakeが、プレイリストのような長尺の「アルバム」をリリースして、音楽ストリーミングサービスでのチャート成績を狙っている。それらも必要だろうが、アルバムとして通して聴くことを想定して作られていない。
個人的には、そういったリリース形態は楽曲一つひとつのポテンシャルを下げてしまっているように思えてならない。計算された曲順とアルバムの長さで、ストーリーや空間を演出する。
数百とある曲の中から絞り込み、作品を作る。これがアルバムというアートの美しさであり、プリンスが語っていた重要性ではないのだろうか。
現に、本当に優れたアルバムならばチャート成績を狙って沢山の曲を詰め込む必要はない。カニエウエストがリリースしたアルバム”Ye”はたった7曲しか入っていなかったが、その曲全てがチャートを独占した。
頭からシャッフル無しで、何もせずにただアルバムを聴く。そんな贅沢な音楽との向き合い方ができるのは、この世界的混乱がくれた産物ではないだろうか。
今週はアメリカから発信された、あなたを別の世界に連れて行ってくれるアルバム達を紹介したい。
“Anak Ko” by Jay Som (2019)
インディーロックという今ではメジャーなジャンルに、自分が目覚めたのは高校2年のときだった。それまでポップやヒップホップなどしか聴いておらず、あまり他ジャンルを開拓することに興味がなかった。
自分の知っているエリア、心地いいエリア(英語では”comfort zone”と言われ、よく使われる表現)にステイしがちだった自分の性格上、あまり冒険をして来なかった。
だが、その時は少しだけ何かが違った。今回の「コロナブレイク」同様、きっと今までより遥かに時間があったからだろう。とにかく今まで聴いたことない音楽を求めて、有名音楽レビューサイトのPitchfork(ピッチフォーク)に掲載されていたアルバムを眺めていた。
そこでそのおしゃれで部屋に飾りたくなるアートワークに惹かれ早速聴いてみたのが、自分をインディーロックの世界に誘うことになったジェイ・ソムの歴史的名盤、”Everybody Works”であった。
カリフォルニアをベースに活動するジェイ・ソムことメリーナ・ドゥテルテが放ったそのデビュー作は、映画かのような感動的なラストを迎えるアルバムだった。それから2年が経ち、待望のセカンドアルバムがリリースされた。
”Anak Ko”はタガログ語で「子供時代」という意味で、母から”Anak Ko”と呼ばれたテキストをタイトル案にしたという、フィリピン系アメリカ人というルーツを根底に感じさせるエピソードもすかしてなくて好印象。
アルバムの二作目というのは、そのアーティストのこれからを示すという意味で重要である。二作目がいいものは大体いい。マイケルジャクソンの世界一売れたアルバム「スリラー」は彼のソロ二作目だし、トイストーリーの二作目も面白かった。
その「2」というトリッキーなジンクスに囚われることなく、あえて今までの大きすぎないスケール感を残し、唯一の大きな変更は今まで彼女自身が叩いてドラムや他の楽器を、他の人にお願いするようになったことぐらいである。
このアルバムのために20曲用意したが、それらを全てボツに。そして、さらに12曲書き上げた中で選ばれたのが、この9曲というなんとも念密に、こだわって作り込まれたアルバム。
前作の成功によって、週6でレストランで働く生活から、世界中いろいろなところを周る生活に一変したというメリーナ。もちろんプレッシャーを感じることもあっただろうが、自身の中での変化について、「お酒を飲まなくなったことで、ある種の逃避がなくなった。そうしたらチャレンジを正面から受け入れられるようになった。」と言う。
そうして作られた今作は、全体を通して「過去と今の人間関係が交差する」というテーマが伝わってきた。1曲目の”If You Want It”で少しずつ自転車のスピードを上げて、まだ朝の薫りが残る田舎道を走り出す。
ギターソロパートは少し荒い道を乗りこなすかの如くワイルドな一面が伺える。そしてその流れのまま先行シングル”Superbike”へ。これはまさに「Jay Som節」と言える、爽やかで太陽が水面に反射するようなナチュラルなキラキラ感が聴いていて気持ちいい。
そこから少しトーンダウンして、アンニュイな雰囲気が漂う中盤。”Tenderness”はそのハイライトだろう。今の関係性に問いかけるような歌詞が、まさに一人旅の途中とか、常に駆け抜けてきた日常に突然訪れる「漠然とした疑問・不安」のフェーズを上手く表現していると思う。
そんな中にも”Nightime Drive”とか”Devotion”といったテンポのいい曲を挟むことで、暗すぎない構成を保っているのは流石。タイトル曲”Anak Ko”である種の「Lowest Point」にたどり着くのだが、そこで彼女は何かを見つけて、またさらに進み出す。
もう吹っ切れて、また強くなったのが”Crown”でわかる。その名の通り「冠」を裸の王様にあげて、自分はもう次に行くわ、と言った感じ。
そしてやっぱり、最後は家に帰ってくるような安心感と優しさで幕を閉じてくれるのが”Get Well”。「関係は終わってしまったけど、あなたもあなたでよくなってね。私もサポートするから」という、嫌味もなく本心からくるその別れにすがすがしさと甘酸っぱさを感じる。
しかし、ここでの「あなた」は、俯瞰から見た自分に言っているのか、ものに言っているのか、それとも誰かに語りかけているのか。
そう考えるとっても深いし、聴き手にストーリーを委ねる姿勢はすごく優しい。うーん、青春!やっぱり彼女の作品は映画のように胸に迫ってくるものがある。
“Sucker Punch” by Sigrid (2019)
Jay Somはロサンゼルス発のアーティストとして、彼女のアートを世界中まで届けてくれた訳だが、その逆もあると思う。つまりその影響を受けたアーティストがアメリカ外で生まれるということだ。
ノルウェー生まれの24歳、Sigrid(シグリッド)のアルバムは、「とにかく明るい音楽」にどっぷり浸りたい時におすすめだ。このアルバムも、アルバムカバーを見た時から気になっていたが、今回の休みでやっと聴くことができた。
よく「本は表紙で判断するな(”Don’t judge books by cover”)」と言うけど、自分的に正しくは、「本は表紙を『よく見ないで』判断するな。」ということだと思っている。
今回、このアルバムを聴いてその考えは裏付けされたように思える。このカバーを見ると、一見素朴で落ち着いたサウンドを想像する。
しかし、いざ中を開けて見ると、そこにはホイットニーヒューストンやシンディーローパーのような往年のポップを図らずとも連想させる「キラキラなドラマチック感」と、Alessia CaraやHailee Steinfield、Hayley Kiyokoのようなまさに「ナイーヴで輝く青春」というような、現代のサウンドプロダクションが巧みにミックスされた、超王道ポップ揃いなのだ。
なるほど確かに、よくカバーを見てみると、彼女の強い意志はその瞳に現れているし、彼女の周りに置かれた色鮮やかな石(?)はそのきらめくサウンドを連想させる。
予想やイメージなんて悠々と飛び越えていくその姿に、これがデビューアルバムだということを忘れてしまう。彼女の曲はとにかくどれもドラマチック。
1曲目の表題曲”Suck Punch”は今時のポップサウンドなのだけれど、流石アデルを自身のアイドルとするだけあるケタ外れの歌唱力が目立っている。そこから徐々にテンポを上げていって、”Mine Right Now”、”Don’t Feel Like Crying”といったパワフルなシングル曲が矢継ぎ早に繰り出される。
どれも爽やかで太陽光が似合うサウンドに、心を少しずつオープンにしていきながら、ルールや型にはまらない「ありのままの自分」を一貫して表現している歌詞も流石。”Level Up”で少しテンポを落とした後の、”Sight Of You”で響くストリングスには思わず胸が「うっ」となる。
ポジティブな別れから見える新たな世界が、青春映画で主人公が夜道を全力疾走するようなサウンドと一緒に表現されている。「曲を書く時は、いつもドラマチックさを大切にしている」という彼女。めちゃくちゃ狙い通りな聴き方してるよ。すごい伝わってるよ…。
次の曲”In Vain”では、あるひと/ものへの存在に戸惑い、「あの時の私の気持ちはどこに行ってしまったのか…。」と物思いにふける。アコースティックサウンドに彼女の歌唱力なんて、鳥肌のカツアゲである。少しリズムを帯びてきたと思ったら、後半1分の彼女の感情の爆発には食らってしまった。
彼女をスターダムに押し上げたヒット曲”Don’t Kill My Vibe”でその感情は更なる高みへ登ったかと思えば、前半で歌った”Mine Right Now”と対をなす”Never Mine”を持ってくる構成にも、アルバムとしての力量を思い知らされる。
アルバムが進むに連れて、どんどんフィルターを外して感情を露わにしていく。「出会った頃とは何かが違う。変わったのは私?あなた?」そんなテーマがこの作品に一貫しているように思える。
ここまで重厚なサウンドプロダクションを乗りこなしてきたが、最後の一曲”Dynamite”でピアノと自分の歌唱力だけで表現する姿には、自身のポテンシャルを存分に発揮して、彼女の未来を示しているように思えた。
こんなデビューアルバムを持ってくる天才だから、マルーン5(ちなみに彼らはカリフォルニア出身!)と一緒にツアーを周るのも納得。ストレートに響く歌詞と、いつまでも頭の中を跳ねるサウンドはこれからも自分たちの心を解放してくれるはずだ。
”IGOR” by Tyler, The Greater (2019)
こうして自分が聴いてきたアルバムを眺めていくと、2019年というのは音楽的に豊作な年だったとよく分かる。前に紹介した2枚は、タイプの違った名盤であることは間違いないし、期待されていた作品だった。
だけど正直、この”IGOR”というアルバム程、この年の関心を持っていったアルバムはなかったように思う。もしあなたがアメリカの音楽、いやアメリカという国の「文化」に興味があるのなら、このアルバムを聴かない手はない。
タイラー・ザ・クリエイターこと、タイラー・グレゴリー・オコンマはまさにカリフォルニアから世界に飛び出していった。フランクオーシャンやThe Internetといった才能がごった煮の2010年代の重要ヒップホップグループ、Odd Futureの創始者でありリーダー、そしてプロデューサーの彼はこの2010年代にグループ活動と並行して自身のソロアルバムをそれまでに4枚リリースしてきた。
そんな10年間の締めくくりとして、図ったかのようなタイミングで満を辞してリリースされたのが初の全米ナンバーワンとグラミー賞を彼にもたらしたこのアルバムだったのだ。今ではConverseとのコラボスニーカーや自身のブランドGolfを街中で見かけることも多い。
そんなカリスマと化した彼が今回表現したのは、かなりパーソナルでセンチメンタルなものだった。前作”Flower Boy”で自身のパーソナルな部分を全面的に表現し始めて、ファレルウィリアムスやリルウェインといったヒップホップのオリジネーター達はもちろんAnna Of The Northやジェイデン・スミスなどの新生アーティスト達をも巻き込んでの傑作に仕上げた。
今回もビヨンセの妹で、アーティストのソランジュ、カニエウエストやシーローグリーンといった豪華なメンツを揃え、何層にも重なった複雑すぎてシンプルにも聞こえるサウンドを操りながらラップを披露していく。だが今作で今までと大きく異なったのは、彼が歌声を披露したところだろう。
ケンドリックラマーに歌声を褒められたことも、彼の背中を押したという。今まで書き溜めてきた楽曲や、リアーナ、ジャスティンビーバーなどに提供予定だった楽曲などを染め直しレコードに収まる40分という尺にそれらを詰め込んだ。
一曲目の”IGOR’s Theme”で地面に響きそうなノイズと共に、今にもIGORの影がゆっくり見えてきそうな壮大な幕開け。そこからパッと光が差すように始まるヒットシングルの”Earfquake”で、溢れる恋について人類は彼とその恋人しかいないんじゃないかという程真っ直ぐに、情熱的に歌いあげる。
”I THINK”ではもう「好き」がこじれてきて、これは本物の愛だと確信するのだがそれを伝えることができないジレンマに苛まれている。確実に相手との時間は無くなってきている(”RUNNING OUT OF TIME”)中、相手との別れへの不安は募っていく(”NEW MAGIC WAND”)。
自分への自信は無くなってきて、もう距離をとってしまおうかと歌う”A BOY IS A GUN*”のアグレッシブかつ切なさが残る銃声と対照的に、”PUPPET”では抑えきれない愛をカニエウエストと一気に暖かなメロディーと共に歌う。
そこから一気に殺意すら感じられる、マシンガンのようにアグレッシブなビートが血流を3倍速ぐらいに高めてくる”WHAT’S GOOD”で、好きになったことを後悔するが、後半に「光」を見て何かを悟る。”GONE, GONE/THANK YOU”で何と我らが日本代表、山下達郎の”Fragile”をサンプリングしつつ、「もうあなたはいなくなってしまったけど、今までありがとう。」と別れを受け入れる。
こんなに明るくて優しいメロディーなのに、どこかまだ中身がなくて、気持ちがついていっていないように聞こえるのは気のせいか?そう思っていたら、”I DON’T LOVE YOU ANYMORE”と叫びながらどうにか自分の気持ちに折り合いをつけようと自分と格闘していて、こちらも納得すると同時に共感。
聴いているこちらも胸が張り裂けそうになるのだけど、そこで大人になって、相手とは友達でいようという答えにたどり着く”ARE WE STILL FRIENDS?”は、夕焼けが電車の帰り道に差し込んでくるみたいにあったかくて、ほろ苦い。
そしてIGORの成長と気持ちの移り変わりをここまで間近で見られたことに感動してしまう。今作を通して描かれる「相手」は常に「He」だということも、今のアメリカらしいというか、この10年でのLGBTQ+の動きが影響しているようにも取れる。
何よりJ-POPや”A Girl Is A Gun”といった映画などの様々な影響を受けたこの作品が、アメリカで受け入れられたのは感慨深いものがある。
今週はここまでにして、来週にアメリカを感じられるアルバムをまた紹介したいと思う。