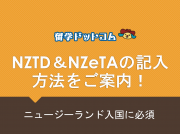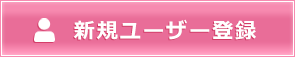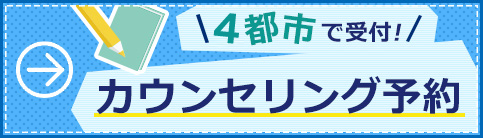アルバムというプラットフォーム ~アメリカから世界に(後編)~

最近、自分が子供のころウルトラマンが好きだったのを思い出した。めちゃくちゃにのめり込んで、ヒーローの名前は全部言えたし、光線系の名前も覚えていた。
とにかく名前に強かったのは覚えている。「そう言えば好きだったなー」とぼんやり考えていたけれど、なぜそこまで好きだったのかは思い出せなかった。
なんだかモヤモヤして、インターネットで当時のオープニング映像とかを見てみると、「あーこれこれ!」というなんとも言えない安心感と懐かしさに出会った。
そこでなぜそこまでのめり込んだか思い出した。正確には、その時分かっていなかったけど今なら分かる。
それは「ひたすらに手の込んだ芸術」が好きだからだ。特撮作品は、今では日本を代表するカルチャーだし、アメリカはもちろん世界中で愛されている。
だが特撮映画、ましてやテレビシリーズはそのあまりに凝った作業とたくさんの機材やジオラマ、セットを要するため、「作れば作るほど赤字になる」と言われている。CGやコンピューター技術の発達により、その工程はより非現実的なものへとなってしまった。
だが一つ言えるのは、「手が掛かる」ということは、「情熱を要する」ということ。
長いドミノだってそうだろう。別にやらなくても誰も困らないし、かなり地道な作業だ。だけどそれでもやるというのは、そこに強い意志があるからなわけで。
そんな情熱をたっぷり注いで作られた作品たちは、世代を超えて愛される。特撮はもちろん、映画や音楽にもそういった作品はたくさんあるのではないだろうか。
自分はずっと、情熱に惹かれて生きていくんだろうなと思っている。そんな自分がおすすめしたい、アメリカを感じられるアルバムを今回も紹介したいと思う。
”It Is What It Is” by Thundercat (2020)
音楽の世界だけじゃないだろうけれど、「横の繋がり」というのはどこでも大切だ。それは相手が上の立場だから立てるとか、引っ張ってもらうとかそういうことでもなく、相手が下だから面倒を見るという訳でもない。
あくまで同じ列に並ぶものとして、となってくると建前がめっきり無くなってくる。別に立てる必要も、面倒を見る必要もない。放っておいてもいいかも知れない。だけどそれでも声をかける時というのは、その相手が本当に優れた何かを持っているから。
それは横の繋がりだからこその、真正なジャッジができる状況だ。特に芸事の世界では、そうして互いを高めあうことは多いのではないだろうか。芸人の世界でも、同期が先に自分たちより売れて、嫉妬をするものもいれば、その売れた同期から新たな機会をもらうこともあるという。ダンスの世界も、そういう話を聞いたことが何度もある。
では音楽の世界ではどうか。カリフォルニア出身(本当にカリフォルニアは化け物級のタレント揃い)のベーシスト、サンダーキャットことステファン・ブルーナーもそういった横の繋がりで引き上げられた、隠れスターだった。
2015年のラップ界、いやジャズやフュージョンといった他ジャンルを巻き込んでの傑作アルバム「To Pimp The Butterfly」をケンドリックラマーが製作した時、彼のビートと歴史深いサンプリングの数々の中でしっかりとベースで作品の軸を支えていたのは、他でもないサンダーキャットだった。
ここで見せた超人的なグルーヴ感と、トリッキーかつ正確なプレイは誰もが注目せざるを得なかった。だからここで彼がグラミー賞受賞者の一人になったことは当たり前の流れだと思う。
人々がやっと、サンダーキャットというとてつもない才能に気づいたその時に出されたソロ前作の「Drunk」はもちろんヒット。ケンドリックやファレルウィリアムス、ウィズカリファなど豪華で誰もが知っているアーティストを客演に招き、新たなジャンルのリスナーも獲得した。
そこから3年、満を辞してリリースされたのが今作である。前作がもし、夜道をバーからの帰り道に一人で歩く印象だったとしたら、今作は一人でまだ見ぬ地に旅立つ夜といった印象だろうか。そんな今作はどこかミステリアスでありながら、夜中飛行機に乗って旅に出る感覚。
ゆっくりと荷物を整え、空港に向かいながらこれからの旅に備える1曲目から、2曲目で一気に世界が動き出す。これまでゆっくり動いて見えた人々も、すっかりスタスタと歩き出す。3曲目の”I Love Louis Cole”もそんな雰囲気を継承しつつ、彼の余裕のある鷹のようなファルセットヴォイスと、随所で見られるえげつないベースプレイがポップなメロディーといい意味でアンマッチ。
”Black Qualls”ではSteve LacyとChildish Gambinoを招いて至極のグルーヴにダイブさせてくれる。そのまま前作の空気感を継承した浮遊感溢れる5曲目へ続くと、6、7、8曲目は短いながらもタイプの違った、彼のベースの独壇場。ユーモア溢れる「機内放送」から続くシングル曲、”Dragonball Durag”でようやくテイクオフ。
優雅で余裕たっぷりのプレイはファーストクラスの気分にさせてくれる。10曲目から、機内で振舞われるお酒に酔ってしまったのかはわからないが、少しダークな空気に一転。”Fair Chance”ではタイダラーサインのコーラスが妖艶に響く中、じっとりとベースを鳴らす。
きっと彼は誰か想う人を残して、飛行機に乗り込んだのであろう。”Never be the same”と繰り返されるタイダラーサインの声が妙に脳に響くのは自分だけだろうか。
未来への不安から自分を落ち着けているかのように、”I know I’ll be alright”と歌う”Existential Dread”から、今ある現実を受け入れて、前進する覚悟を決めた、その名の通りの”It Is What It Is”でこの旅は終わりを迎える。
「新たなスタート」を思わせる勢い溢れるエンディングは、なんとも清々しい。
あなたもこのアルバムという飛行機に乗って、過去から未来へ飛び立ってみてはいかがだろうか。
“Apollo XXI” by Steve Lacy (2019)
自分が音楽を開拓したい時、よく「芋づる式」を活用している。これはもうやっている人も多いだろうが一応説明しておくと、例えば一人の好きなアーティストがいたとして、その人と仕事をした人や、その人の憧れている人、関係がある人などをひたすらに調べて聴きあさっていくというなんともオタク的な活動である。
ギタリストであるSteve Lacyは、そうしたオタク活動をしていく中でどうしても避けては通れない存在だった。彼は前に紹介したThundercatの楽曲にも参加していたし、ケンドリックラマーの現時点の最新作「Damn」にも楽曲を提供している。
そしてタイラー・ザ・クリエイターがリーダーのグループOdd Futureに属するグループ、The Internetの中心メンバー(つまりタイラーのグループの中のグループに属している。うん、ややこしい!)でもあるSteve。
ここまで自分の好きな作品に参加しているのだから、当然彼の名前はこのソロアルバムが出るまでに目にしていたし、このアルバムの存在もリリース直後から知っていた。
だけどその時は「今じゃない」という謎の自分の声から、ダウンロードしておいたアルバムを数ヶ月前まで寝かせていた。なんだかその時点で自分にとってはすごく不思議なアルバムである。話が個人的になり過ぎたところで、少しカリフォルニアの話をしたいと思う。
というのも、ThundercatやTyler、ケンドリック、Jay Somと同じくSteveもカリフォルニア出身なのだ。確かにカリフォルニアは日本と同じぐらいの大きさを持つ州だから、それだけアーティストが生まれても不思議ではないと思うかも知れない。
だけど彼らの音楽には同じ空気が流れているような気が自分にはする。この「カリフォルニアサウンド」は、ネオソウル/ファンクの故郷サンフランシスコ、ヒップホップのメッカであるコンプトン、様々な文化が入り乱れるロサンゼルスといった都市によってバラエティに富んだ音楽的バックグラウンドがあることが関係しているのではないかと思う。
Steveは治安が悪いことで有名なコンプトン出身だが、この小洒落た音にはどこか育ちの良さが見えるなぁと思い調べてみたところ、彼は私立の学校に通っていた厳格なキリスト教徒だったということを知って、なんだか妙に納得。自分と同い年で誕生日も1日違いの21歳が、こんな完成度の高いアルバムでデビューしていると知って正直怖くなっている。
1曲目の”Only If”は「もし僕がタイムトラベルできたなら」という歌い出しに相応しい、浮くように軽いギタープレイと力の抜けたボーカルでゆっくり始まる。そこからのコントラストが鮮明な2曲目”Like Me”では、荒くもグルーヴィーにドラムが響く。「僕と同じやつはどれぐらいいる?/僕と同じく友達を失うのを恐れている奴は、どれぐらいいるんだい?」と大衆に語りかけている。
これは彼がバイセクシャルであることをカミングアウトした時の心の内を歌っているのに違いない。クリスチャンとして、この叫びは彼の心の中で大きなものだっただろう。曲調が変わる後半で、彼はその叫びと共に少し高いところに登って物事を俯瞰で見ている。
「僕達みんな消えていくんだ」と何かを悟った後、そこから宇宙に飛び立つように勢いよく始まる3曲目。男女関係(Playing around:はっきりせずに遊びの関係)と子供の時に遊んだ遊具(Playground)を上手くかけているセンスはさすが。
そのままスペーシーでファンキーな雰囲気が続く4曲目から、ギタープレイが光る5曲目へ。宇宙において、「僕が案内してあげる」と連れ出すと、そこから二人の世界に繋がる6曲目。スムーズで優しいサウンドがまた美しいコントラストを生み出している。そこから心を開いたのか、彼は自身の恐れ(7曲目)や欲望(8曲目)、愛する前の焦りを抑えようとする葛藤(9曲目)などプライベートなところも語り出す。
10曲目の仲睦まじい会話から始まるインスト曲で、ありのままの彼が相手に受け入れられたことが分かる。そこからのキラーチューン”N Side”で、彼は伸びやかなギタープレイと巧みな比喩表現を使って彼女の気持ちを確かめる。
そこからの無重力感漂うラストトラックでは、今までの全てが夢だったのかと思わせたり、彼は旅から帰還して愛の下では自分がどう行動するのかを学んだりとか、聴くタイミングによって受け取り方が大きく変わりそうなエンディングだ。スムーズとグルーヴのコントラスト、自己解放と疑心暗鬼が大きく入り乱れるこの宇宙への旅は、”Apollo XXI”を聴くことで誰もが体験できる未知の体験だ。
“Not Too Late” by Norah Jones (2007)
子供を妊娠中に聴く音楽は、お腹の中の子供にも影響が及ぶという話を聞いたことがある。クラシックを聴かせると頭が良くなるとかそういう類のもあるし、その子がどんなセンスになるかというのも影響するらしい。確かに自分の母は、自分を妊娠中にR&Bを聴いていたそうで、その時がなぜか一番そういうジャンルを聴いていたという。
なので、自分が今洋楽やR&B好きになってなんの不思議もないし、なんだか説得力もある。だけどそれは、妊娠中だけの話じゃないようにも思える。子供の頃に聴いてた曲って、覚えていなくてもどこかで意識には入っているものだ。ミュージシャンとかのインタビューでよく「小さい頃からビートルズを聴いて育った」とかいう話を聞くけれど、それがその人の音楽性を顕著に影響しているから面白い。
あと最近、YouTubeのコメント欄を読むのにハマっているのだけれど、これがなかなか面白い。昔の曲でも、「2019年でもこれを聴いてる人はいる?」みたいなくだらないコメントから、「私が小さい頃、よくお母さんと車の中でこれを一緒に歌ったわ。」なんていうほっこりするコメントもあるものだから、同じ曲でもたくさんのストーリーがあるのだと思い知る。
自分にとってノラジョーンズは、懐かしさと心地よさのシンボルだ。きっと多くの人が同じことを言うだろうが、自分らの世代(ちなみに自分は1998年生まれ)は、同意してくれる人が多いと思う。
ニューヨーク出身のノラが、マイルスデイヴィスやジョンコルトレーンを抱えるジャズの名門レコードレーベル、ブルーノートレコードに所属して、デビュー作にしてグラミーをもたらすことになった、「Don’t Know Why」を収録した大ヒットアルバム「Come Away With Me」がリリースされたのが2001年。当時自分は3歳だったが、彼女のアルバムは聴いたことがあった。
それからリリースされた2作目「Feels Like Home」は2004年リリース。ミレニアム世代の自分たちにとって、ノラの音楽は「新鋭ジャズシンガー」の音楽ではなくて、「気が付けば流れていた」音楽なのだ。往年のジャズファンは、彼女のカントリーやポップが組み合わさった音楽性をジャズと呼ぶのに疑問を示した。
だが自分たちの親世代の当時の若者は、彼女の多様で受け入れやすいジャズを歓迎した。そうして彼女が2007年にリリースした今作は、初めてノラが全体的に曲を作ったアルバムだ。ヒットにも恵まれて順風満帆だったが、他人の作った曲を歌い続けるのはメンタルへの負担も大きかったらしい。
休養期間を経て、ある意味彼女のこの「ファーストアルバム」がリリースされた。ちなみに、自分は母からこのアルバムを借りて、初めてノラジョーンズ、というかジャズの楽しみを知った。このアルバムのアメリカらしさは、「リアルなニューヨーク感」だろう。
サウンド面でも、全体を通して優しいピアノのサウンドとキャッチーかつ切ないメロディーが、忙しい都会の喧騒によく映える。いきなり別れから始まる1曲目”Wish I Could”は確かに切ないけれど、別れは新しいスタートだよとノラから言われている気がする。
「Like the oyster cracker on the stew/We’re the golden crust on the apple pie」といったなんともアメリカンな食べ物を使った情景描写にも唸ってしまう2曲目で、もう自分はニューヨークに住んでいる。生活感たっぷりの雰囲気から一転、太陽と時間の尊さとを上手くかけた3曲目はメルヘンだけどリアル。
4曲目の歌い出しで「You’ve got a famous last name/But you’re not to blame/Baby I see you for who you are(あなたは昨晩有名になった。だけどこれはあなたのせいじゃないわ。あなたが本当にどんな人かを見たんだもの)」という歌詞は、アメリカンドリームが溢れるニューヨークなら、あながちメルヘンでもないのかも知れない。
5曲目の”Not My Friend”なんて、都市で生活したことなら共感できる友情へのジレンマを女神のようにきらきら歌っていて胸にうっと迫る。8曲目の”My Dear Country”ではダイレクトに2004年の大統領選挙とその後の心境を歌っている。政治に手を出すのはいつだってリスキーだけど、それを混乱と希望を表現したピアノプレイと共に、アートに昇華したノラにあっぱれ。
だけど現実的になり過ぎずに、11曲目の”Little Room”ではニューヨークの代名詞である狭いアパートでの生活を、コミカルかつ可愛く歌っている。バイナル盤ラストの13曲目”Not Too Late”で話ているのはきっと、1曲目に別れたあの人。「Tell me how you’ve been/My cup is full of no love/Not too late or love(今までどうしてたか教えてよ/私のカップは愛がないことで溢れているの/愛に遅すぎるなんてことはないでしょう)」なんて言って、最後はまた結ばれるのかな。
CD盤収録の”2Men”は、お互い違う日にキスをした別々の男性二人が、同時にバーにいるのを発見してしまった女性の話。茶目っ気と気品たっぷりに歌うノラにうっとりしていたら、このアルバムは気が付けば終わっている。
食べ物や人間関係、部屋や政治までも題材にして、ニューヨークに住んでいる彼女ならではのリアルを表現した今作は、フィクションのようだけど実際はたくさんのニューヨーカーの日常なのかも知れない。